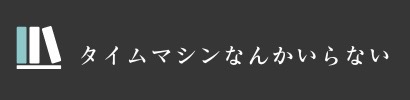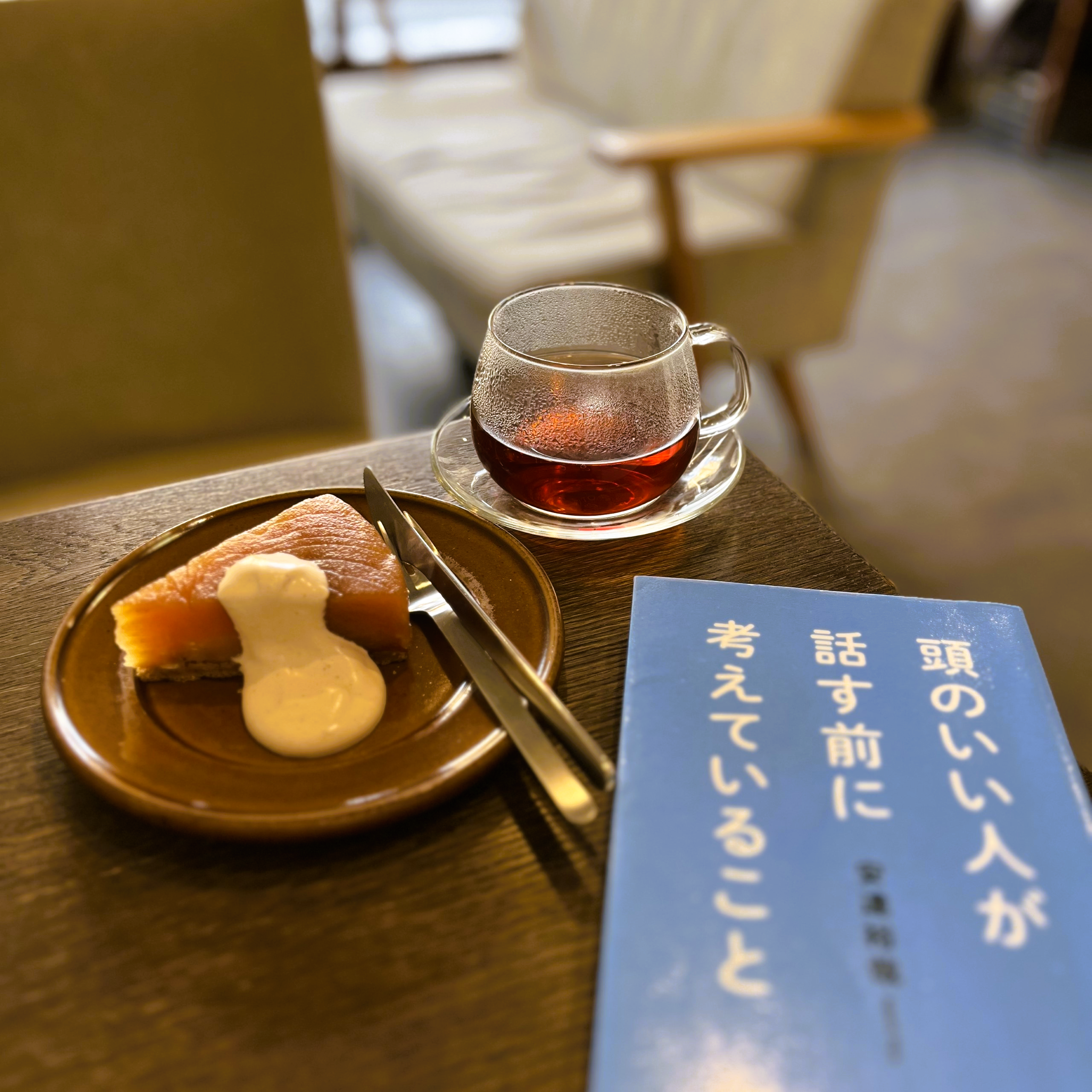頭のいい人が話す前に考えていること 安達裕哉
| 読書時間 | 1時間10分(6日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 流行りの本が好きな人におすすめ度 | ★★★ |
私はこの本がビジネス書のベストセラー1位だと聞いて恐れ戦いている。
みんななぜこの本を読むのか?
そんなに頭が良く思われたいのか、馬鹿だと思われたくないのか、謎である。
頭の良さは一朝一夕でどうにかなるものでもない。
ちょっと喋ればその人の本質は透けて見えるのだから、アホかそうでないかなんて取り繕いようがない。
特に大人になればなおさらだ。
この本が悪いということではない。
書いてあることは論理的でわかりやすい。
でも、長らくビジネス書の1位になるのがわからない。
なぜなら、頭のいい人はこの本を読まなくても「頭のいい話し方」をしているし、そうでない人がこの本を読んだからと言って「頭のいい話し方」が簡単にできるとは思えないからだ。
この本では、頭のいい人の話し方の黄金法則として、感情的にならないこと、信頼を得るためにきちんと考えること、目の前の相手ではなく課題と闘うこと、伝え方よりも考え方の不足を気にすること、知識はひけらかすものではなく誰かのために使うこと、承認欲求は満たす側になることを挙げている。
つまりは「ある程度の知識の貯蓄をして、物事を判断できるだけの十分な情報があり、情報を整理できる能力と正しく深い傾聴力があること」ということだ。
実に正しいことを言っている。
頭がいい人というのは「こちらが1、2くらい伝えれば、MAXの10理解してくれ、かつそれに解決策をすぐ提案してくれる」と私は感じている。
これは「結局、他者が何を言おうとして、何を求めているか」を瞬時に理解できる能力があるということだ。
それは内容がスピーチであろうが会話であろうが、文章に変わろうが、媒体は何になってもあまり変わらない。
よって頭のいい人は、聞く力だけではなく、読む力も高いと私は思う。
つまり「頭がいい話し方」ができる人は、聴解力と並んで読解力も高いと言えるのではないか。
喋りは上手で面白いけれど、こっちの言いたいことをてんで理解できない人はいるが、聴解力と読解力があって、話し方が壊滅的な人は見たことない。
話す能力というと、言う・聞くの二つのスキルだけと思われがちだが、私は読解力も大きく関わっていると思うのだ。
だからこそ、話が下手くそな人は読解力も乏しい可能性が高いと思っている。
よって、本を読んだとしても、その内容を正しく理解し、実行できるかどうかは未知数だと思っている。
そして、話し方は聞いてくれる人のスキルで大きく変わるということも忘れてはいけない。
優秀な人が聞き手だと上手く話せる時がある。
結局、頭が良くなければ「頭がいい人の話し方」はできないのである。
この本は小手先の話の上手さを磨く本ではなく、本質的に「頭がいい人の話し方」ができるように説いた本である。
これから読もうとしている方は、ぜひこの本の本質の部分まで読んでいただきたい。
世の中には簡単に何かができるようになることはほとんどない。
本質的に良くなるには時間と精神力がいるのである。