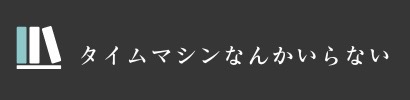職場で傷つく~リーダーのための「傷つき」から始める組織開発 勅使川原真衣
| 読書時間 | 1時間16分(4日間) |
| 文章の難易度 | ★☆☆(読みやすい) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 職場で傷ついたことがある人におすすめ度 | ★★★ |
みんな、職場で傷ついている。
「職場で傷つくこと」についてスポットを当て、日常に起こっているのに「ないこと」になっている「傷つき」とは何か、なぜそれに声を上げられなかったのか、そして「職場で傷つくこと」を当たり前にしないために個人や企業ができることは何かを書いた本です。
組織に何が必要かよりも「何が妨げになっているのか」に目を向ける必要性が書かれています。
題名に「リーダーのため」とありますが、リーダーじゃなくても全く問題なく読める本です。
大なり小なり、みんな職場で傷ついたことはあるでしょう。
しかし今までは「能力が低いから仕方ない」「弱いから傷つくのだ」つまり「個人の落ち度によって傷ついたなどと言うのだ」という発想によって、何とも乱暴なのですが、みんなが「傷ついたこと」に声を上げられずにいたそうなのです。
個人の素質よりも組織の「関係性」に課題がある、というのが筆者の主張です。
漠然とした「能力の高さ」を一人一人に求めるのではなく、個々を観察して、その人の存在に感謝する姿勢が組織において大切だと書かれています。
私が普通の企業に勤めていて思うのは、総合的に見て、やっぱり「明らかに能力が高い人はいる」よな、ということ。
人間性も良いし、何をやってもどこへ行ってもある程度頼りになる人というのは、やっぱりいます。
そういう人は、やっぱり組織にほしいです。
そして、おそらくその真逆も存在しているということ。
ただ、能力関係なくいつの時代にも誰にでも経験があったはずの「職場で傷つくこと」を個々人の素質のせいにしてしまっていたゆえ、職場で傷ついた人自身すら「傷ついたこと」を重く考えられなかった。
結果自分以外の人の傷つきにも、深刻に考えられずに今日まで過ごしてしまったことはあると思うのです。
そして、個人の素質というのは多くの場合不安定なもので、環境によって左右されることがあります。
その人の決断が環境を生むのではなく、環境がその人に決断させることがあると私も思っています。
昔は今より労働人口の確保が容易だったので、人をふるいにかける、みたいなこともできたでしょう。
それが必ずしも過去の負の遺産とは思っていませんが、今はとにかく人手も人材も不足しています。
加えて、定年退職の年齢は延びており、昔よりも長い年数、仕事を続ける必要が出てきました。
年金支給額も、今より減る可能性の方が高いでしょう。
一人一人の労働負担は心身とも増えているのに、給料は伸びず、年金も頼りになるかわからない。
これだけ生きる環境が変化している中、組織内の感覚だけが昔のままではひずみが出る方が自然だと私は思っています。
「傷つき」に理解が進まない理由の一つとして、私は、何事も悪用する人がいる、ことがあるのではとも思います。
「傷つき」というのは、目に見えず、数値化ができるわけでもありません。
そういうものは、盾にして悪用する人が必ずいます。
本当に被害を被った人が、ますます声を上げられない状況を作ってしまうのです。
このような悪循環があることも忘れてはいけないと思います。
またこの本にも書いてある、「大人の対応」が環境の改善を阻害する可能性について、とても同意ができました。
本当は傷ついているのに、言わずに流したことが、組織での気づきや良くなる機会をつぶすことがあるということ。
言い方に気を付けながら、未来のためにも事象に向き合い、発言する機会を逃してはいけないと思います。
人は、大切なものを大切にされなかった時に「傷つく」と書いてありました。
すごく共感しました。
相手に悪意はないのにすごく傷つくことがありますよね。
悪意がないから許されるわけではないのですが、何ともモヤモヤするでしょう。
感謝するより前のできていないこと、まずは目の前の人を「軽んじないこと」が私は一番大切なのではないかと思いました。