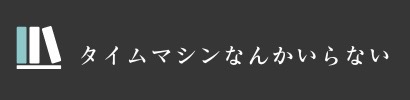生成AIスキルとしての言語学 誰もが「AIと話す」時代におけるヒトとテクノロジーをつなぐ言葉の入門書 佐野大樹
| 読書時間 | 3時間9分(8日間) |
| 文章の難易度 | ★☆☆(わかりやすい) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 生成AIが使う「言葉」を知りたい人におすすめ度 | ★★★ |
生成AIの特徴の一つは、自然言語でやり取りができることが挙げられる。
つまり専門用語ではなく、いつも話していたり書いたりしている言葉で使うことができるということ。
これは生成AIを使用するにあたって、皆が使ってみたいと気軽に挑戦できる状況を作っていると思う。
生成AIは、社内の文化が全くわからない状況で今日入社してきた能力値が高い新入社員のようなものだと私は思っている。
優秀だが、共通の文化はないから、まずはお互いの考え方や手法のすり合わせは必要になる。
しかし同じ言語を話し、意思疎通はできるものだから、一瞬そのことを忘れてしまう。
Chat GPT-4が話題になり、私は架空のプレゼンテーション資料を作ってみたことがあった。
あっという間に資料はできて、体裁は良く、ボリュームは想像以上だった。
しかし、求めていたものはこれじゃない感も否めなかった。
これは生成AIの能力値では決してなく、使う側、つまり私の指示が何か足りなかったのだと直感でわかった。
私の「AIに対しての言い方」が悪かったのだ。
どんな言葉でどんな風に指示をすれば的確なのかを知れば、もっと生成AIの本来の良さを使いこなせるのではないかと思い、この本を読んでみた。
この本では、生成AIはどのように「生成」しているのか、どのように言語を理解しているのか、なぜ言語学を学ぶことが生成AIを使用するうえで有利なのか、具体的にどのような言語指示を出したらどのように答えが返ってくるのかを解説している。
この本を読むと、生成 AI は上位層の特定の誰かだけが使うツールではなく、今自分がしたいことほとんどのアシスタントができることがわかる。
スマートフォンのように身近な存在になっていくのかもしれない。
ちなみに本で使用されているのは Google Bardだが、生成AIの共通した概念が書かれていることが想像されるため、ほかの生成AIでも十分活用できる知識だと思う。
なんでもそうだが、自己流と経験値だけで何かを活用するとなると成長は遅くなる。
仕組みを理解することが近道である。
自分のより良いパートナーとなるよう、生AIと付き合っていく方法がこの本でわかる。
この本を読んで思ったのは、著者の頭の良さである。
難しいことを理解しやすいよう簡単に説明できること、体系的にわかりやすいこと、流れとして頭に入ってきやすいこと、すべてが完璧な本だった。
こんな頭の良い人がGoogle にはいるんだな、世界って広い。
と改めて感動した。