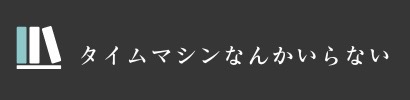欲望の見つけ方 ルーク バージス
| 読書時間 | 2時間55分(7日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 本当に自分が欲しいものは何かわかっているつもりの人におすすめ度 | ★★★ |
体調を崩し、それがなんとなく長く続いていた時、「何が欲しい」とか「何がしたい」とか、そういう気持ちが極端に薄れた。
欲望とは心身の健康から生まれるものではないかと思った。
だからこの本を読んでみようと思ったのだが、まずは斜め上の答えが待っていた。
人は真似することを通じて、ほかの人が欲しがるものを欲しがっており、必ず誰かの影響を受けている。
そして人が欲しがることを欲しがるという行為は競争が生まれ、競争はさらなる模倣を生む。
というルネ・ジラールの模倣理論を軸に、他者の模倣による欲望とはどんなものか、それとどう付き合うのがいいのか、ということがこの本で説かれている。
人は本来、欲望に突き動かされて生きていると言ってもよい。
自らのものだと思っている自分の欲望は、自分から湧き出たものではなく「他者の模倣」である。
模倣の欲望には際限がなく、「欲望は、常に自分に欠けていると感じるものに向かい、苦しみをもたらす」という。
模倣の欲望からは逃れられない。
しかし、それを理解できれば、生活のあらゆる面で活用できる。というのが著者の主張である。
「争いは、違いからではなく、同じであることから発生する。」そうで、「力の根はたいてい模倣の欲望にある」らしい。
そして、競争は利益を薄める。
欲望の影響は個人レベルにとどまらない。
ひとりの欲望は誰かから影響されており、そのひとりの欲望がまた違う誰かに影響を与える。
つまり、集団のありかたも変えるのだ。
著者は、欲望にはポジティブなサイクルも存在し、それを機能させることが必要だと言っている。
それには、能動的に行動し、自分でうまくやったと思える、充足感をもたらすことが重要で、深い意味と充足感を得た瞬間が大切とのこと。
欲望を単なる欲しているものと軽く考えず、価値ある欲望を考えることは未来を変えることだそうだ。
「『欲する』というのは『愛する』の別の言い方なのだ。」そうだ。
この本では、具体例を多数挙げ、他者の模倣の仕組みとその影響、集団の心理を解説している。
しかし、私が知りたかったことと相違があるからか、読んでいても何となくピンとこなかった本だった。
欲望が自分からは湧いてこないとすると、私の欲望が薄くなったのは、他者との関係に意識が向かなくなったからだと考えられる。
他者の模倣は際限がなく、悪い影響もあるが、ベースとして元気でないと成り立たない。
欲望があるというのは、良いものであろうが悪いものであろうが健康な証拠だと私は思っている。