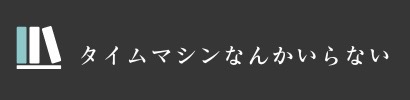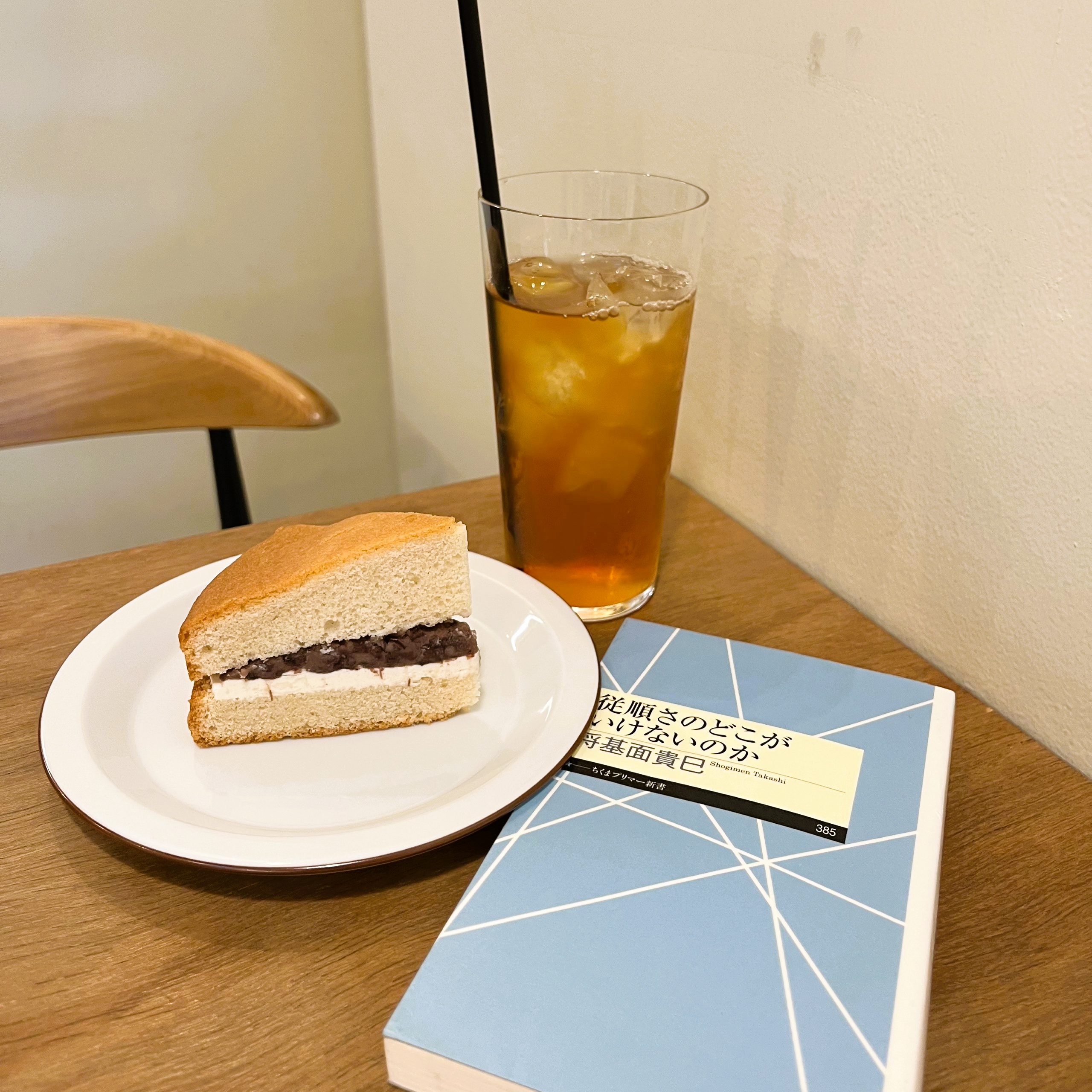従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳
| 読書時間 | 1時間17分(5日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 日本のサラリーマンの皆様におすすめ度 | ★★★ |
私は、従順さそのものが悪いとは思っていない。
この本を読み終わっても、その考えは変わらない。
そもそもの問題は、人の良心からくる何かの上に胡坐をかいたり、悪用したりする人がいるということだ。
それが横行した結果が、今日の日本そのものを表しているとも思っている。
それを少しでも良い方向にもっていける可能性があることを、この本は詳しく述べている。
この本が警鐘を鳴らしているのは、みんながそうだから、ルールだから、先生が言ったからなど「思考停止を伴った従順さ」についてだ。
政治、思想、歴史的観点から、人間がなぜ権威に服従しがちなのか、それがなぜ問題なのかを解説している。
理不尽な出来事を見て見ぬふりをしたり、誰かの意見にただ従うだけでは、社会の問題は根本解決には至らない。
これは、頭ではわかっていても、なかなか行動につながらないものだということは私もなんとなくわかる。
この本では、身に振ってかかる事柄が「不正」によるものなのか「不運」によるものなのかを見定める必要があり、不正には声を上げる必要性を説いている。
また、人は権威や権力に服従することで、安心を得たり、自分で決断したりしなくてよくなったりするので、責任から逃れられると思い込んでしまうことがある。
しかし、自分で意思決定ができることが、本当の自由であることを忘れてはいけないのだ。
「とりあえず自分に危険が及んでこなければそれでよい」や、何かが起こっても「しかたがない」と考え、楽な方に流され、歪んだ結果になった今、果たしてこれから状況が改善されることはあるのか、という不安も拭えないだろう。
だからこそ、これ以上悪くなるのを避けるために何をしたらいいか考えて、それを少しすつでも実行していくことが必要なのではないかと思う。
不正には怒っていいのである。
怒らないことや黙っていることが、大人の対応とか美徳であると、都合よく植え付けられた考えに騙されてはいけない。
この本の言う通り、「他人はともかく自分は」という姿勢をまずは持つことが必要なのだ。
異論を咀え、簡単には服従しない人々の伝統が大きな潮流をなしてきた歴史についても、この本には書かれている。
では具体的にはどうしたらいいのかというと、「自分の良心」と「共通善(人々が共通に善いものとみなすものであり、ある共同体全体の利益を意味する)」に基づいて、決断や行動をするということだ。
そして、一人一人が不正に対して声を上げ、行動することの重要性が説かれている。
それが社会を変える第一歩なのだ。
もし、今の自分の置かれている状況、もしくは日本の状況に何か違和感を覚えているのなら、一つの答えがこの本には書いてある。
過去は変えられない。
しかし、これから先の未来は変えられる可能性が残っていることを忘れたくない。