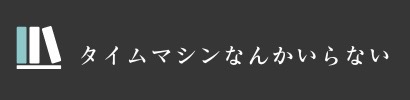口の立つやつが勝つってことでいいのか 頭木弘樹
| 読書時間 | 1時間42分(5日間) |
| 文章の難易度 | ★☆☆(読みやすい) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| ここぞという時に言葉が出てこない自分が口惜しい人におすすめ度 | ★★★ |
バーナード・ショーは、沈黙は軽蔑を表すと言った。
シェイクスピアは、沈黙は喜びの前触れと書いた。
言葉にならない気持ちの大きさや複雑さは古からわかっているはずだが、今の時代はどうだろう。
言わなければ伝わらないと言われ、それならと頑張って発言すれば論理的に矛盾している、などと言われる。
だから現代では「口の立つやつ」が勝ってしまう。
この本は、言葉で表しきれないけれど、言葉以上に複雑で深い気持ちの存在について書いてあるエッセイだ。
言葉にできることなんて氷山の一角だということは、私たちもよくわかっているのに、現代ではそれが忘れられかけている。
そもそも言葉にならないことだって、バーナード・ショーやシェイクスピアが言ったように、そこに何もないわけではないのに。
さて、私はこの本を読んで「情緒の奥行き」というものを考えた。
何かを体験した時に、その事象についてどのくらい広く深く思考がめぐり、その体験から引き起こされる様々な感情を思い出せるかを私は「情緒の奥行き」と呼んでいる。
想像力プラス、自分が以前経験した感情を呼び起こし共感できるか、というようなイメージである。
感情の再現性の豊かさと言ってもいい。
この本にあるように、誰かを非難する前に「もしかしたら、何か事情があるのかも」と考えることは、「情緒の奥行き」そのものだと思う。
奥行きはある方がないよりは良いと私は思っている。
この「情緒の奥行き」の広さはどんな要素と比例しているのか考えたことがあるが、答えがなかなか見つからなかった。
通っていた学校の偏差値が高かったり、裕福な家で生まれ育ったり、お金をたくさん稼いでいたり、社会的地位が高かったり、そういう世間で「ないよりはあったほうが良い」と思われている要素では測れない。
だから、似た人が集まるだろう学校や会社でも、情緒に奥行きがある人とほとんどない人がいる。
「情緒の奥行きが狭い=無神経」とも言えない。
情緒の奥行が広いことは、繊細とか器が大きいことともかなり違う。
辛い経験や、思い通りにならないことが人生に存在し、それを諦めず、自分で乗り越えてきたかで奥行きが出るのかもしれない。
乗り越えた、というと解決したような印象になってしまうが、辛いことや思い通りにならないことと共存して、生きていくことを受け入れることもある種乗り越えることだと私は思っている。
このエッセイを読むと、その「情緒の奥行きが広いことの素敵さ」を思い出せるのである。
説明できない気持ち、矛盾した行動、思いがけないこと、自分特有の生きにくさ、人間らしくてすごく素敵じゃないか、と思う。
この本は、生きていく上で何を大切にしたらいいのかをもう一度問いかけてくれる。
最後に、この本に好きな文章が二つあったので、引用したい。
「本との本当の出会いは、読んだときではなく、その本を思い出す体験をした時なのかもしれない」
読んだ時はピンと来なかった本が、人生を経た何かのきっかけで思い出されることがある。
これは読書の醍醐味だと私も思う。
これから先の生涯で、どれだけの本を私は思い出せるだろう。
「失えないものを失って混乱してしまった世界に秩序をもたらす、それこそが文学の力だと思う」
何か大切なものを失って、様相が変わってしまった世界で生きていくためには、新しい物語が必要だとこの本には書いてある。
人生において心の支えになってくれるのも、また本の力の一つだと私は思っている。