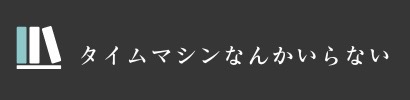人魚が逃げた 青山 美智子
| 読書時間 | 1時間44分(4日間) |
| 文章の難易度 | ★☆☆(読みやすい) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 銀座によく行く人におすすめ度 | ★★★ |
「僕の人魚が逃げたんだ。この場所に」
銀座の歩行者天国で、西洋貴族風の出で立ちをした王子がこう言って、物語が始まる。
は?王子??と思ったあなたは、まんまと著者の手腕に巻き込まれたと言っていい。
この小説には、5人の男女の物語がそれぞれ短編として書かれ、それが一つの物語を構成している。
どの物語も銀座という街を通しながら、少しずつ他の誰かの物語にリンクしている。
先の王子は、さしずめアンデルセンの「人魚姫」の王子様のような雰囲気や言動を見せており、王子は5人すべての物語に登場し、登場人物と重要なやり取りを行う。
ファンタジー色はところどころ強いのだけれど、核心は人間の「愛情のターニングポイント」の話だ。
恋の物語も出てくるけれど、「愛の話」だという方が私にとってはしっくりくる。
人が誰かに抱く愛情は、輝かしいものだけれど、決して一面的なものではなく、必ず切なさや、やるせなさが同居する。
そして、誰かと誰かの間に育まれた愛情は、「片方の誰かからは見えないもう片方の誰かの想い」同士で成り立っている。
それがこの本では静かに美しく書かれているのだ。
この物語を読むと、「自分が恐れている状況は自分が思っているほど悪くはないのではないか」とも思わせてくれる。
そして、人魚姫の王子様が愛する人を間違えてしまったように、人間は誰にでも、愛する人に対して目が曇ることもある、ということだ。
相手が言葉に出さないけれど、ふとしたところで見せた言葉や行動、その裏にどんな気持ちが隠されているのか、注意深く寄り添っていれば問題はおこらない、という簡単な問題でもない。
愛情と対峙するには、そういう傲慢さも捨てなければならない。
好きだからこそ、その思いが高鳴りすぎて、本来見えるはずのものを見えなくしていることがあるからだ。
自分の経験とも重ねて過去を思い出すに至り、すごく切なく、でも温かい気持ちでこの本を読んだ。
本を読まない妻が作家である夫に言う台詞がある。
「あなたが書いた一行で人生が変わる人がいるかもしれないんでしょう?」
好きなものが違っても、見ている世界が違っても、相手を理解して愛することの本質をよく表しているなあと、うるっとしてしまった。
そして、この本の物語のすべてが銀座という街で起こったこと、とされるのが、憎い設定である。
銀座は、どこか多面的であり、文化と包容力があり、でも銀座という本来の自分の姿を見失わないオーセンティックな街だ。
そして、この本でも何度か「時計」や「時間」がフォーカスされたように、過去から現在の時間の重なりの中に、人々の記憶と感情が大切に眠っている街だと私は思っている。
銀座にいると、あの日、あの時のあの想いを、カセットテープのように再生してくれるようにも感じることがある。
どこか思わぬ時空の歪みがあるとしたら、どこかのビジネス街でもなく、どこかのブランドショップが立ち並ぶ街でもなく、どこかの若者の文化が生まれる街でもなく、やっぱり銀座なのではないかと私は思う。