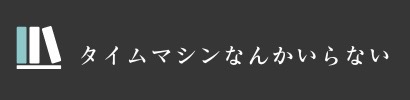モチベーションの心理学 鹿毛雅治
| 読書時間 | 6時間22分(7日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 他者のモチベーションを上げたいと思っている人におすすめ度 | ★★★ |
本を読んでいる時の「気付き」には二種類あると思います。
一つ目は目から鱗的なもの、頭をハンマーで殴られたような衝撃がある新しい発見です。
二つ目は自分の感覚や経験から、きっとこうだろうなあとぼんやり考えていたものが研究結果の記述などから正しかったことがわかるもの、眼鏡をかけて視界がはっきり見えるようになった感覚になるものです。
この本は後者の眼鏡のような本。
モチベーションはどのように生じ、何に影響を受け、変化しいていくのか、目標があればいいのか、それとも自信か、成長か環境かなど理論を整理し紹介されています。
私はだいたいのことについて、とにかくやる気が続かない。
意欲も湧きやすい方ではないと思います。
一般的に人を褒めてやる気にさせるとか言われているのを、「そんなのでやる気や成績が上がるんだったら世話ないよ」と思って見ていました。
実際、褒めてもらったからこそやる気を削がれたことが私にはあったからです。
これは私個人の性格が特別曲がっていたからではなかった!
褒めたからと言って、人はやる気になるほどモチベーションは簡単な構造ではないと、この本に書いてありました。
ただ褒めることより物事を出来るように指導してあげることが必要とか、他人の評価などの外的要因のモチベーションより自分の興味などから湧き出る内的要因のモチベーションの方が長く続きやすいなど「そうだよね、そうだよね」と思いながら読みました。
ちゃんと研究で結果が出てるじゃない、私の感覚は正しかった!と嬉しくなった本です。
あと「学習性無力感」についても注目したいので書きますね。
これは、いくら自分が行動しても望む結果が得られないという体験の積み重ねによって「やっても無駄だ」という日随伴性認知が成立してしまったために無力感に陥ること。
このように体験を通して無気力を身につけてしまう現象を学習性無力感というそうです。
やっても無駄だろうとわかっていることにやる気なんて湧かないよ、ということですね。
残念だけど、これは日本ではよく起こっていることなのかなあとも思いますね。
そして無力感の原因を作っている人が「モチベーションを上げろ」とか無神経に言うのだろうなあと想像できます。
これをしたら絶対的にモチベーションが発生するとか上がるということは難しく、複雑に要素が絡み合っているのがモチベーションというもの。
むしろ他者に対して何をしてあげたらいいのか、という視点でこの本を読むと役に立つかもしれません。