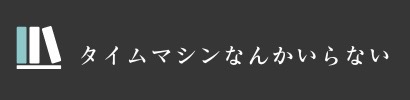さみしい夜にはペンを持て 古賀史健(著), ならの(イラスト)
| 読書時間 | 1時間47分(3日間) |
| 文章の難易度 | ★☆☆(読みやすい) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| みんなといても孤独を感じる人におすすめ度 | ★★★ |
書くことは、自分の中にある本当の思いと向き合うこと。
この本は、「ありのままの自分を好きになりたかった」タコの中学生タコジローが、ヤドカリのおじさんと出会い、文章、とりわけ日記を書くことを勧められ、それを通して、自分と置かれている状況を見つめ、受け入れていく物語だ。
タコジローは、周りに誰もいなくて感じる「子どものさみしさ」ではなく、ひとりじゃないのに感じる「おとなのさみしさ」を感じ始めている。
「おとなのさみしさ」は周りの人々の中において、自分が自分でいられないことに悩むことだとこの本では言っている。
それを「書くこと」が助けてくれる。
「ぼくたちはたくさんのものを見て、聞いて、感じている。けれどそのほとんどは、意識のなかからすり抜けていく。そういう「すり抜けていく感情』をキャッチする網がことばなんだ」と、ヤドカリのおじさんは言った。
話すことは思いつくままできるが、「考え」の伴わない文章はない。
書くことが面倒くさいのは、頭を使って、自分なりの答えを見つけ出さなくてはできないことだからだ。
どこか孤独を感じた時にこそ、頭を動かすこと。
浮かんでは消えていく自分の思いを顕在化するように「考え」にすること。
それには書くことが効果的なのだとこの本では言っているのだと思う。
それが「さみしい夜にはペンを持て」なのだ。
タコジローと同じ目線を持つような、子どもから大人への階段を上り始める高学年以上向きの児童書だと思うが、大人が読んでも実りのある本だ。
子どもであろうと、大人であろうと、自分と向き合うことの必要性と重要性は何も変わらない。
本当に辛かったら逃げても良い、と大人は言う。
しかし、どこに、どうやってということまでは説明されない場合が多いし、逃げるのだって勇気がいることだ。
我慢することより、一時的にはすごく勇気がいる。
今が「逃げるべき本当に辛い時」なのかどうか、自分では判断がつかないことだってあるだろう。
ダメだとわかった時は、迷わず一刻も早くそこから逃げて欲しいと私も思う。
もし、その前に何かできることがあるとすると何なのか、とも同時に考える。
その時、手を差し伸べてくれる本だと思った。
誰もがタコジローのように、状況が良くなるとは限らないのはわかっている。
ここまでやってダメなのだから、やっぱりダメだと踏ん切りをつけるための一歩になるかもしれないと思うのだ。
ヤドカリのおじさんは「答えは見つけるものじゃない。出すものだ。いまの自分が『あのときの自分』の感情に答えを出す。
あのときの自分はこうだったはずだと、答えを決める。そうやって決めないことには、なにひとつ書けないんだ」とタコジローに言う。
人生において「なんとなく」に流されてはだめな時があるのは、大人になれば実体験としてわかるだろう。
もちろん、答えが簡単に出せないことだってある。
正しい答えなんてないかもしれないが、自分にとってはどうだったのか、自分なりの答えを出す。
それが出来ている人と出来ていない人は、生き方も大きく違うと私は思う。
違っていたって良い。
いつか答えが違ったと思ったら、正しい答えを上書きできる。
誰の為でもない、自分自身の考えなのだから。
この本では、何をどう書いたらいいのか、という話も出てくるので、一体何を書いたらいいのかと悩んでいても大丈夫だ。
私は「自己肯定感」という言葉が好きじゃない。
自分を大切にしたり、前向きに捉えたりすることは必要だと思うが、この「自己肯定感」という言葉を使ったとたん、暴力的なものを私は感じる。
なぜなら図々しいことや、自己主張が悪い意味で激しいことが「自己肯定感」と紙一重だからだ。
また自己肯定感を意識した瞬間、自己を肯定できていない自分から逃れられなくなる。
だから、自己肯定なんて忘れてしまって良い。
大切なのは、ちっぽけで拙いけれどどこか愛おしいはずの、ありのままの自分と向き合うことだ。
自分と向き合う姿勢が、自分以外の人と向き合う土台になる。
この本でも書かれている通り、自分であろうとも、他人であろうとも、大切なのは「わかってもらおうとすること」と「わかろうとすること」二つの努力だ。
「このふたつが重なり合ったとき、ようやく「わかり合う』という状態が生まれる。」のだ。
私はそれが知性の第一歩だとも思っている。
誰かと上手くいかないと思う時、その「誰か」よりも、まずは「自分」と向き合うことの大切さを教えてくれる本だ。