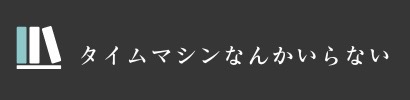「頭がいい」の正体は読解力 樋口 裕一
| 読書時間 | 1時間48分(5日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 頭がいい人と自分は何が違うのか知りたい人におすすめ度 | ★★★ |
前、ある本を読んだとき、頭の良さの要素とは何か考えた。
私は、誰かの話し方なんかより、何かを読む力の方が頭の良さを感じる。
話し方は訓練すれば一瞬はごまかせる。
プレゼンテーションや演説は練習すればするほど上手くなるのが良い例だ。
でも読解力はごまかせない。
「読む力」というのは単に書いてある文章を理解するだけではなく、文脈を理解する、つまり書いてあることを元にその背景を含めた全体像を、理解および判断できる力だ。
そんな考えがあったから、この本を読んでみたのである。
この本の内容は、裏表紙にすべて書いてある。
本1冊分の内容を端的にわかりやすく網羅している、本当にすごい文なので、引用したい。
ものごとを正確に読み取り、理解する力=読解力。文章を読んで考えをまとめたり、会話で相手の意見に反論するときなど、あらゆる場面で不可欠だ。しかし読解力の無い日本人が増えている。読書量の不足やネット記事・短文SNSの普及による「長文を読み解く体制がない」「言葉の意味は知っていても使いこなせない」ことが主な原因だ。本書では、問題を解きながら実際に言葉を使い、文章を書いて「語彙力」「文章力」「読解力」の3ステップで鍛えていく。飛ばし読みや資料の要約、会話やコミュニケーションにも役立つ、現代人の必須スキルを磨くー冊。
前読んだ本にも書いてあったが、「読むことは思考すること」だ。
本からそのまま引用すると「文章をたどれないということは、他人の思考をたどれない、つまりは他人の思考について思考できないということにほかならない。
言い換えれば、自分で考えることができないということでもあるだろう。」ということだ。
読解力がないと極論生活に支障をきたすわけだが、私は人間が読書という「人類が数百年前から行ってきた楽しみを味わうことができなくなる」ことが、すごくもったいないと思っている。
そしてそれは複雑な人間の心や関係性、社会のあり方、世界の構成や、今起こっていることも理解できないことにもなる。
せっかくこの美しい世界に生まれて、皆等しく死んでいくのに、それを少しも理解しないまま終わるのは何とも淋しい、と私は思う。
じゃあどうしたらいいのかと言うと、ただ本を読めばいい、というような簡単な問題でもない。
もちろんたくさん本を読むことは読解力をつける上で重要な一要素だが、それだけでは適わない。
そこで著者は「文章を書くこと」を勧めている。
例えば、サッカー経験者と未経験者が同じ試合を見ても、理解度や解像度が違うのは想像できるだろう。
多くの場合、サッカー経験者の方がより深くその試合を見られるように、文章を書けない人よりも、書ける人の方が読解力は高いはずだ、というのが著者の主張である。
この本の中には、文章を読むだけではなく、書く実践問題もあるので、具体的な書くスキルもつけられるようになっている。
私は本も読んでいるし、自己流とは言え、こうやって日常的に文章も書いているし…などと多少の自負があったのだが、自分の苦手な文章表現が明らかになる。
読み飛ばさず、実際に解いてみることをお勧めする。
読解訓練の最終問題は何と慶應義塾大学の入学試験問題が出てくる。
これだけ急に難しい。
かなりの本気を出さないと読めない文章である。
受験問題というのは、いつも使っている頭の筋肉とは全く別のところを働かせないと解けない。
これを主に10代の学生が解くのだから、受験とは大変だ、と改めて思った。
さてこの本では、文章を書くことの実践編として、読後感を発言するのも勧めている。
このサイトには願ったり叶ったりの意見である。
しかしながら、私は著者の勧めているようなきれいな定型では書けないので、そこはお許し願いたいのだった。