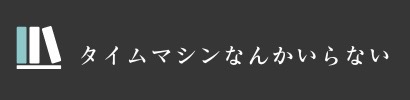漢字と日本人 高島 俊男
| 読書時間 | 3時間49分(6日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★★(難しい) |
| いつも何気なく話している日本語の本質について知りたい人におすすめ度 | ★★★ |
「中国人が旅行先に日本をよく選ぶのは、同じく漢字を使っている国だからだ。彼らは漢民族として漢字をとても誇りに思っている」。
嘘か誠か、いつだったかこんなことを聞いたことがある。
だから、むしろ「漢字と中国人」みたいなことを知りたかったのだが、たまたま目に入ったのがこの本だった。
面白い本だった。
この本は、まず日本語の「同音異義語」について触れている。
「第一志望のコーコーに合格して、親コーコーだ」
これを日本人が耳で聞けば「高校」と「孝行」を頭の中ですぐ変換できる。
日本人がごく自然にできていることが、いかに日本語の特徴的な性質なのかがこの本を読めばわかる。
漢字は約1100年前に中国から入ってきた。
それまでの日本には言語はあったが、文字はなかったようである。
漢字は、漢族の言語、漢語の文字である。
漢字および漢語は日本語とは無縁であり、むしろ全く違う性格のものだそうだ。
確かに「我是日本人」という中国語を教えてもらった時、「『I am Japanese』の並びじゃん」と英語との類似性を感じたことを思い出した。
日本語にはそういう親戚はいないそうだ。
著者は漢字が日本へ入ってきたことは不幸である、と言っている。
もともと言語としてあった日本語の発達が止まったことと、漢語のためにつくられた文字で日本語をあらわすには不都合があるというの二つの理由だ。
この本では、漢語とはどういう言語か、発音や意味などを説明し、日本語とは相容れない理由を説明している。
また、日本人は日本語をあらわすものとして、漢字をどう加工して取り入れたのかということと、日本語の性質、そして漢字を使ってきた日本人の歴史が書かれている。
この本にあった一例をここに書こうと思う。
Clubを「倶楽部」、Catalogueを「型録」とし、コカ・コーラは「可口可楽」と書くらしい。
音が似ている文字をとりあえず当てて終わりにするのではなく、音をできるだけ再現しつつも、言葉がもつ意味を表現できるような漢字を選択した面白い日本語だ。
俱楽部はゴルフ場の名前でたまに見たことがあるが、こんなふうに意識したことはなかった。
やがて西洋の影響があり、国語改革が行われるにいたる過程のことも書かれている。
それは「明治前半に、過去の日本をすべて否定し、全面的に西洋化しようとしたこと、そこから国語の根本的なまちがいがはじまっている」そうだ。
「西洋の言語学者は、言語は音声であり、文字はそのかげにすぎない、文字は言語にとって本質的なものではない、と言う。」そうで、「人が口に音声を発し、それを耳に聞いて意味をとらえるのが本質」らしい。
つまり、文字は言語の必然ではない。
しかし日本語のみが例外で、同音異義語が示す通り、漢字という「文字のうらづけなしには成り立たない」言語なのだそうだ。
またこの本によると、「中国もまた漢字を捨てようとした」時があるそうだ。
冒頭の私が聞いたことは都市伝説判定をされたわけである。
私たちは日常的に読み書きしている言葉をそこまで深く考えて使っていない。
しかし、この本を読むと、なんと面白い性質をもった言語を私たちは操っているのだろうと感心する。
そして、かなり無理をして漢字を駆使しながら日本語を使っている。
そんな性質をもった日本語がなんとなく好きになれる本だ。
この本の著者は、批判を多少気にしつつも、ズバズバと言いたいことを書いている感じがするのが良かった。
「です・ます調」と「だ・である調」が混在していて、文章自体も個性があった。
思わず、巻末の発刊年を確認してしまったほどだ。
この本は2014年に発刊されたもののようだが、今だったら校閲をこのままスムーズに通るだろうか。
著者の思想がよくわかる本というのは、賛否両論ありながら、だいたい面白くなる。
今はお亡くなりになっているのが残念だ。