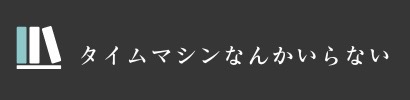センスの哲学 千葉 雅也
| 読書時間 | 3時間23分(7日間) |
| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |
| 内容の難易度 | ★★★(難しい) |
| センスがないと思っている人におすすめ度 | ★★★ |
センスが良い、悪いは、日常でもよく会話に出てくるが、このセンスというものを明確に説明するとなると厄介だ。
才能、選択、感性、価値観、どれもセンスを説明するには合っているようで、でも何かそれだけでは足りない気がする。
だからこそ、センス、なのだと思う。
皆がなんとなくぼんやりとわかっているけれど、これだと明確に説明できないもの。
このサイトでは「センスを上げる大人の読書」を一つのポリシーとしている。
読んでみるしかない本だ。
この本はセンスというものの定義から始まり、センスを良くするにはどうしたらいいのかが書かれている。
センスとは、物事の直感的な把握であり、様々なジャンルにまたがる総合的な価値判断のことを言う。
あるものに出会った時、その意味や目的ではなく、その「形」を把握することがセンスだと定義されている。
何かを見ようとする時、人間は意味を考えてしまう。
そうではなく、純粋な「形」を見てみるということ。
目に見える物理的な形状だけではなく、音などの響き、味、触った感触も含めて「形」としている。
そしてその「形」は「リズム」だと表現できる。
リズムは凹凸で構成されていて、そのでこぼこを感じるのがセンスだとこの本では言っている。
このリズムは、2種類あり、一つは0→1のような存在の、あり・なしを行き来するもの。
もう一つはうねりとされる。
センスは意味を超越し、まずはそのリズムを把握することなのだが、意味についてもリズム的なとらえ方ができる。
意味には距離があり、言葉の意味の遠い、近いでまたリズムができる。
(対義語は遠く、類義語は近いなど)
つまり良いセンスとはまずは意味や目的だけでものを見ようとせず、そのもののリズムを楽しむこと、そして次に意味をとらえる時にも、リズムを感じ取ること、となる。
センスとは、何かに固執せず、時間をかけて目の前のものごとと向き合えることなのではないか。
センスの良い人とは器の大きい人と言い換えられる気もする。
人間は安定性を求める中で、それだけだと退屈して、不安や不快を適度に感じるほうが「面白い」と思ったりする。
この本でも人間の二重性について書かれている。
私はその二重性という言葉がすごく良い言葉だと思った。
人間は矛盾を持った二つの感情を行き来することがある。
好きだけど憎い、しなくてはいけないのに面倒くさい、嫌いなのに依存する。
それを矛盾ではなく、二重性と呼べばしっくりくる。
人間は、その二重性こそが面白いのだと私は思っている。
この本は特別厚くもなく、文体も柔らかく、内容も大変わかりやすく書かれている。
だから、手にとって読んでみよう、と思える。
しかしながら、全体を理解しようとするとすごく難しい本である。
文体が話しかけるような形だから、難解な内容に一見感じない。
気をつけろ、みんな。
覚悟して読んだ方がいい。