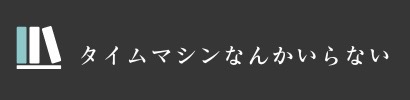街から書店が減っている。
古本屋になれば尚更だ。
図書館不要論も聞く。
それは紙の本が減っていてデジタルに移行していたり、ネット書店での買い物が増えているのだろうと想像できるので、一概に本が読まれていないわけではないだろうが、私は淋しい気持ちになる。
ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」は、主人公のバスチアンがいじめられた時、古本屋に逃げ込んだことから物語が始まる。
私はこれがすごく意味のあるエピソードだと思っている。
何かの理由で心身とも追い詰められた時に、咄嗟に逃げ込める場所はどこだろう。
家でもなく、学校でもなく、会社でもない第三の場所。
もちろん、シェルターのような存在があることもわかっている。
しかし、その「手前の場所」というのが必要なのではないか。
思い立ったらすぐ行ける場所だ。
決意を持って最終手段として逃げ込む場所ではない、いつ行っても良い逃げ場所というものが。
今いる場所から逃げ出したい、と声を上げるのは勇気がいる。
そして一緒に逃げようと言ってあげる方にも勇気がいる。
だから、そう言わなくても行ける場所の必要性を私は感じている。
そのため、シェルターというような名前がついていないことと、逃げ込む場所ではない他の名目がある場所が良いと思っている
しかし現代、そういう場所は、犯罪や闇の温床となることが多い。
悪いことを考えて、狡賢く人を地獄に引き摺り込むような輩はどこにでもいる。
しかし本のある場所というのは、そういう奴が他の場所に比べてかなり少ない。
心身とも孤独な時、悪い輩と関わらないのはすごく大切なことだ。
だから、バスチアンは古本屋に駆け込んだのだと思う。
この理由から、書店や図書館は本を売ったり、本を貸し出したりしている以外にも、すごく意義がある場所だと思っている。
特に図書館は、本を買えない状況にある家庭でも、エンターテイメントや流行を知り、そして学ぶことを叶える場所でもある。
だから、私は簡単になくなっても良い場所だと思って欲しくない。
使えるお金は有限であり、優先順位をつける必要があることもわかっている。
しかし、本来の役割を超えた、大切な意義がある場所もあると知って欲しいのだ。